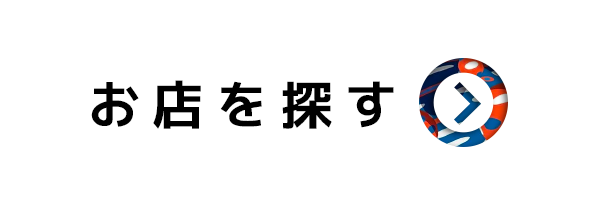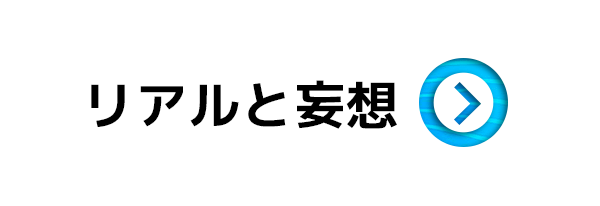ムジ男
ムジ男私が大手化粧品会社に入社して2年目のGW、私と同期の奈緒美のカップルと、
1つ年上のY先輩と妙子先輩のカップルの4人は、熊本県阿蘇市の老舗混浴旅館で小旅行を楽しんでいました。
到着して早々、4人で入浴した混浴の露天風呂で、それぞれ「姦通未遂」に終わった2組のカップルでしたが、少なくとも溜まったままの男性陣はムラムラしたままでした。
皆でそろって夕食を楽しむ間も、私の脳裏には、そこで見た妙子先輩の、少し濃い目のVラインや、Y先輩と手をつないで歩く贅肉のない白い背中と、歩く度にぷりんぷりんと揺れる大きなお尻が焼き付いていました。
夕食が終り、お酒を飲みながら談笑していると、気が大きくなったY先輩が妙子先輩の浴衣の上からおっぱいを触ったり、太ももを弄んだりと、なにかと色々、悪戯を始めました。
「もー。ダメでしょ!お酒弱いんだからー!」
笑いながらY先輩のエッチな手を払いのける妙子先輩の胸がはだけた瞬間、柔らかそうな左側の白いおっぱいが顔を出しました。
彼女がノーブラなのがわかり、私はドキっとしました。
PR
「オレもう、あかんわー。寝るなー。おやすみ」
お酒に弱いY先輩は、12畳ほどの広さの和室の隅に、自分で乱雑に布団を敷くと、ゴロンと仰向けになりました。
気が付けば時計は午後11時を回っていました。
消灯し、私と奈緒美も布団を敷き身体を寄せ、妙子先輩はY先輩に添い寝しました。
しばらくすると、先輩の寝床の方向から、妙子先輩の甘い、かすかな啼き声が聞こえてきました。
私は、抱きなれた奈緒美の形の良い弾力のある乳房を愛撫し、浴衣の裾から手を滑り込ませると既に濡れ始めていたオマンコをゆっくりと攻めました。
「う…ううん…ダメ…」
声を殺しながらあえぐ奈緒美の啼き声と、妙子先輩の、少しハスキーなヨガり声がオーバーラップし、消灯して橙色の光りを残すナツメ球に怪しく照らされた和室に、徐々に声量を上げながら溢れていきました。
「ク…イク!アアン!」
ひときわ大きな妙子先輩の声が響き、彼女は絶頂に達したようでした。
私が、奇妙な雰囲気で明らかに興奮している奈緒美のオマンコに指を割り入れ、ひとしきり手マンをすると、驚くほどあっけなく、彼女もクライマックスを迎えました。
10分ほど静寂が流れた後、妙子先輩がかすれたような声で笑いながら言いました。
「あらら、彼(Y先輩)、寝ちゃったよ…ナオちゃん、お手洗い行こう」
二人は一緒に部屋を出てしまい、その時の私は「女性って、こんなTPOでも『連れション』するんだ」と、心の中で苦笑いしていました。
二人はほどなく、帰ってきました。
所在なさげに仰向けに寝ていた私に奈緒美が言いました。
「ねえ。まだ、元気?」
彼女は、私の右側に横たわり、身体を寄せると、ペニスを握りました。
二人がトイレに行っている間に、私は、発射できずにいたそこを握ったままでしたので、十分に硬く、先端からはガマン汁が出ていたと思います。
ふと、左側を見ると枕もとのあたりに、ロングボブの黒髪をポニーテイルに結んだ、女の子座りの妙子先輩が、私たちの様子を見ていました。
奈緒美は、私の浴衣の裾を開き、反り立ったチンポを剥き出しにすると、顔を寄せ、そこに舌を這わせ始めました。
と、同時に、今度は妙子先輩が自ら浴衣の胸をはだけ、座ったまま両手をついて私の顔を覗き込んだ後、首筋にキスを始めたのです。
奈緒美の舌がペニスを這い回り、カリから先を柔らかい唇で包み、口の中にくわえこんで上下動を始めると、私は徐々に絶頂に近づいていきました。
妙子先輩のキスは首筋から乳首に移動し、周辺を舌先で円を描くように刺激し、時折、硬くなった私の乳首に歯を立てました。
薄明りに照らされて妖艶にほほ笑む彼女は、大きな瞳を潤ませながら何度か私の顔に視線を送り、興奮の度合いを観察しているようでした。
妙子先輩の舌が、私の脇腹の辺りを這い始めると、奈緒美はくるりと後ろを向き、白いお尻をこちらに向けると彼女のオマンコは背面騎乗位に私のチンポを飲み込み、前後運動が始まりました。
「…は…ぁん…ぅんぅ…」
奈緒美が喘ぎ始めると、妙子先輩は四つん這いで私の顔の辺りに覆いかぶさる態勢になり、自ら乳房をつかんで私の顔に近づけ、舌戯を求めてきました。
「ねえ…おっぱい、舐めて…おっぱいにキスして…」
どのくらいの時間が流れたでしょうか。
私は限界に達し、奈緒美のオマンコから肉棒を抜いて彼女のお尻に発射しました。
その様子を見ていた妙子先輩は、ティッシュを抜くと、まだ私の股間のあたりでうごめいている奈緒美のお尻に貼りついた白い愛液をぬぐいました。
「あはは…かわいそう。一人だけ仲間外れ」
妙子先輩が、時々イビキをかきながら部屋の隅で人事不省に陥っているY先輩を見て、明け透けに笑いました。
今思えば、奈緒美と妙子先輩の「連れション」は、作戦会議だったのかも知れません。
いえ、確証はないのですが、私を攻める二人のコンボがあまりにも完璧で、私にはそう思えてならないのです。