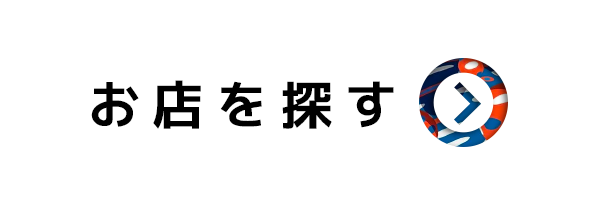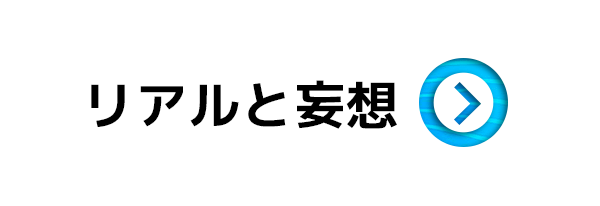ムジ男
ムジ男地方国立大薬学部3年生の琴音は、私とセフレになってかれこれ3年が経ち、真性M女の彼女には様々な調教プレイをしてきました。
その日は琴音が、経験してみたいと言っていた、野外でのアナルセックスをするために、彼女のマンションに車を走らせました。
彼女は、珍しく胸元に付いたファスナーが半開きになって、ノーブラの上乳辺りの白い肌が露出するニットのワンピースに身を包む挑発的な装いで、私を玄関で出迎えました。
今日はどういう心境なのでしょう。
血色感のないマットなファンデーションは彼女の白い肌にマッチしていましたが、レッド系のアイシャドウをたっぷりと使ったアイメイクが特徴的な、今どき流行りの「病み系」メイクは、基本、真面目な苦学生の彼女にはミスマッチに感じました。
「よろしくお願いします。」
「よろしく。きょうは琴音、どんな調教を受けるんだっけ。」
「はい。お外でお尻に入れてください」
「何を入れるの?」
「…Kさんの…オチンポです」
恥ずかしさに俯く琴音の細い肩を抱いて、私は助手席に彼女をエスコートし、地元では有名な活火山の麓の小さな町へと、車を走らせました。
【動画】緊縛調教妻 変態町内会長に見透かされ開発されたマゾ性癖。夫の出張中、縄と蝋燭そしてアナルまで知った誕生日 富井美帆
PR
目的の僻地に着くまでの2時間近くの道中、車窓の風景に田畑が広がり始め、交通量が少なくなると私は調教を始めました。
琴音はワンピースの裾をまくり、助手席に両肘をついてフロントに向かってお尻を突きだしました。
巨尻ではないものの、ぷりんと形のいい、陶磁のように白いお尻が剥き出しになると、彼女は自ら指にゼリーを取り、割れ目に食い込む赤いTバックをずらしてアナルに塗り込んでいきました。
白い、整った病み顔が、少し切なそうに眼をつぶったのを見て、私は車を路肩に寄せて停車すると、助手席で突き出るお尻の中心部の菊門にアナルローターを少しずつ挿入していきました。
「ん…ああ…お尻…少しイタいです…」
「根元まで入ったよ。今から、1時間くらいかな。スイッチ入れるからね」
ブーンと低い音が響くと、琴音はビクンと一度、身体を波打たせましたが、やがて助手席に肘付きの上半身をうずめたまま、Tバックのお尻をくねらせ始めました。
途中、すれ違った車や対向車から、彼女のあられもない恰好が見えていたかどうかは、さだかではありませんでしたが、私は構わず目的地に向かって車を走らせ、琴音は白いお尻を左右に振り続け、途中、何度か股間に自らの指を這わせては「ああん!」と喘ぎました。
目的地につくと、私は、既に利用されていないビニールハウスの骨組みが点在し、荒れ放題の農地が広がる空き地に停車しました。
大きめの石や瓦礫が無造作に散らばる地面にヒールの足元を取られ、よろよろと歩く琴音に、まだアナルローターが中でうごめいているお尻を出すように命じると、彼女は一瞬、躊躇うように周囲を見回しました。
「誰も…いないんですよね…ここ…」
私が無言で、薄いニットのワンピースのお尻に渾身の平手打ちをすると、パアン!と乾いた音がして琴音は「きゃっ!」と悲鳴を上げた後、両手を膝に付き、お尻を突きだしました。
私は、彼女のワンピースの裾を腰の辺りまで捲り上げ、琴音の白いお尻を剥き出しにすると、真ん中に食い込むアナルローターを少しずつ引き抜いていきました。
「あっ!ああん…うう…ん…」
タンポン状のローターが彼女の菊門から抜けると、ピンク色のそれは、先端に僅かに汚物が付いた状態で姿を現し、続けて尻穴からドロっと薄茶色をした粘液が出てきて、白い太ももの裏側に垂れました。
「琴音。お腹の中、お掃除してこなかったの?言ったよね。浣腸しておきなさいって」
「Kさんごめんなさい…私、今朝、お寝坊して…お浣腸1個しかできなくて…」
琴音が言い終わるが早いか、彼女の左右の尻肉に私の平手が連続して弾けて、赤い手形をクッキリと残しました。
「ああっ!お尻痛い!ごめんなさい!ごめんなさい!」
琴音に、自分で肛門を広げるように命じると、彼女は両手を後ろに回し、細い指をお尻の肉に食い込ませながらアナルを割り開きました。
私は、皺が伸び切ってピンク色の粘膜にポッカリと丸く口を開いたアナルに、準備していたイチジク浣腸を3つ、続けざまに差し込み、薬液を流し込んだ後、アナルプラグをねじ込みました。
「うっ…ううん!はぁ…く、…ぁあ!」
さらに琴音のオマンコをまさぐると、そこはもう、ビショビショに濡れて私の人差し指と中指をスっとくわえ込み、かなり乱暴に手マンをすると、彼女は周辺の、閑静な空気を震わせるくらい大きな声で喘ぎました。
「じゃあ、あそこの川まで、この格好でお散歩だね。あそこでウンチ、させてあげるよ」
ベージュのニットのワンピースを腰の辺りまで捲り上げられ、下半身を丸出しにした琴音は、
ピシャン!ピシャン!と白いお尻を何度も平手打ちされながら、追い立てられるように歩き始めました。
「ああ…痛い…痛い!ごめんなさい。ごめんなさい…」
細い顎を震わせ、赤く彩られた大きな瞳を潤ませながら歩く彼女は、自分の心に憑りつく「病み」を払おうとしているように見えました。